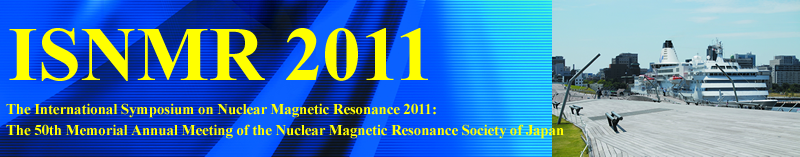
 |
 |
 |
 |
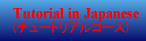 |
 |
![]()
チュートリアルコースについて
NMRの歴史から最近の進歩、動向までを3名の先生方にレビューしていただきます。学生・若手研究者を主な対象としておりますが、一般の方の参加も歓迎いたします。
概要
日 時 2011年11月15日(火)9:30〜12:00(予定)
場 所 大さん橋ホール
参 加 費 無料(下記「事前申込」ボタンよりご登録ください)
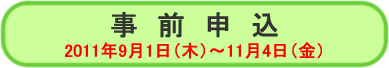
| 講師1 | 図で見る新しいNMR手法の原理 |
| 池上 貴久(大阪大学蛋白質研究所) | |
| この15年間に、さまざまなNMRの手法が開発され、解析に使われてきた。例えば、残余双極子相互作用RDC(残余化学シフト異方性)、常磁性緩和PRE、常磁性シフト(pseudo-)contact-shift、アミドやメチルTROSY、交差相関緩和CCR、緩和分散法relaxation-dispersion、高速測定法(non-uniform-sampling, projection-NMR, single-scan-NMRなど)とMEMなどのプロセス法、動的核分極法DNP、saturation-transfer法などが挙げられる。その中には、もはや新規とは思えない程に日常の解析に多用されている方法もあるが、日頃の忙しさに邪魔され、その物理的な原理までをも勉強するのはなかなか難しい。ここでは、出来るだけ数式を使わずに、「イメージ」でその原理をとらえ、今後のより深い理解の端緒となるようにしたい。 |
| 講師2 | 天然物有機化学におけるNMR |
| 松森信明(大阪大学大学院理学研究科 准教授) | |
| タンパク質のNMR解析といえば主に立体配座解析であるが、天然有機化合物のNMR解析では、平面構造の決定、ついで立体配置の決定へと進み、最後にオプションとして立体配座解析が来る。平面構造の決定はほぼルーチン化しているが、NMRによる立体配置決定は今でも容易ではない。そこで今回のチュートリアルコースでは、NMRによる天然有機化合物の立体配置決定について主に解説する。相対立体配置の決定法には、我々の報告したJ-based configuration analysis法やハーバード大の岸教授らによるuniversal NMR database法がある。また、ご存知の方も多いかもしれないが、絶対立体配置決定法として、楠見教授らによる新モッシャー法を紹介する。さらに時間があれば、膜作用性天然有機化合物について、バイセルを用いた膜環境下での立体配座解析についても紹介したい。 |
| 講師3 | NMRはいかに創られたか: 5. 固体高分解能NMRその1 |
| 寺尾 武彦 (京都大学 名誉教授) | |
| 教科書では長年にわたって積み重ねられた多数の研究成果が系統的に整理され、簡潔に淡々と記述されている。しかし、その行間には先人たちの汗と涙がにじみ、フィクションを超えるドラマが潜んでいる。本講演では時代を画したNMRの方法論の研究にスポットを当て、どのような時代背景の下でどういう人物が何をきっかけに歴史的な発想を得たのか、またどんな困難に出くわしてそれをどう解決して研究を完成させたかを人間的なエソードを交えて話す。若い方々が話を通じて優れた科学者の研究に取り組む姿勢や学問に対する情熱を学んで頂ければ幸いである。 今回は固体高分解能NMRのうち特にcross polarization法について話す予定である。 |
ISNMR 2011 Secretariat
(c/o A & E Planning Co., Ltd.)
9th floor, Shin-Osaka Chiyoda Bldg (Annex), 4-4-63, Miyahara, Yodogawa-ku,
Osaka, 532-0003, JAPAN
Tel: +81-6-6350-7163 / Fax: +81-6-6350-7164 / E-mail: ![]()